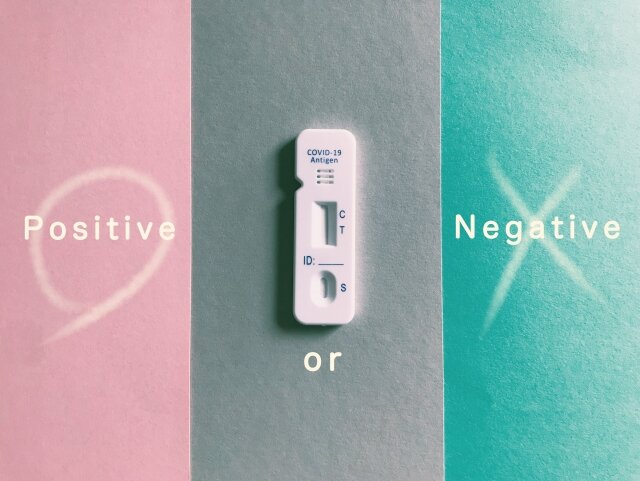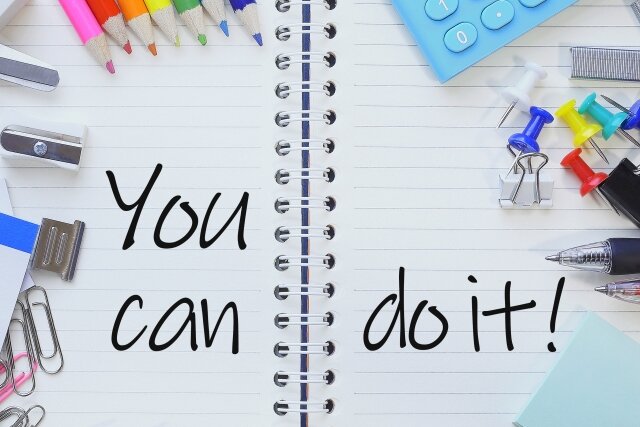産業お役立ちコラム
改正「育児・介護休業法」の施行直前!
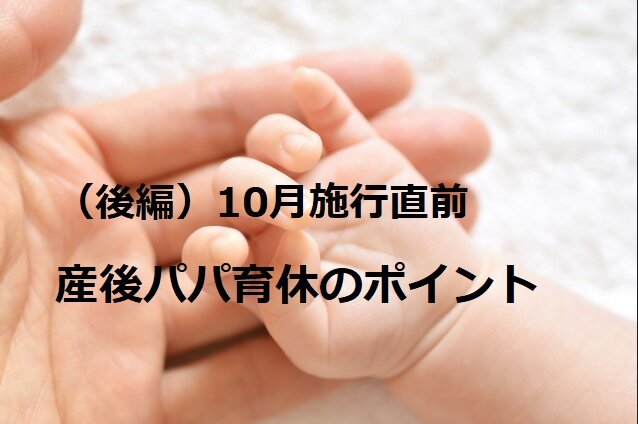
2022年4月に改正「育児・介護休業法」が施行されてから4か月が経過しましたが、法改正に対応した制度の運用は順調に進んでいますか。前編では、産後パパ育休の目玉となるポイントや取得要件についてご案内しました。今回は産後パパ育休中の就労についてと社会保険料についてです。
産後パパ育休中の就労させる場合の流れ
1.労使協定締結
2.本人からの申し出
3.会社から就労日時の提示
4.本人からの同意
5.本人から同意を得た旨の通知
※休業開始予定日までに終わらせること
6.就労
同意したとしても育休開始前までは撤回可能であり、開始後も特別の事情があれば撤回可能。
就業できる日数
就業できるのは休業期間中における所定労働日数の2分の1かつ、所定労働時間数合計の2分の1まで。
休業開始日、休業終了日に就労させる場合は所定労働時間未満まで
📢例えば 所定労働時間が8時間/1日 土日祝日お休みで、14日間の出生育児休業を取得した場合
1日が月曜日で14日の日曜日まで祝日無しのカレンダー考えてみる。
所定労働日数は10日間。10÷2=5日(1日未満は切り捨て)まで就労ができる。
所定労働時間は8時間×10日間=80時間。80時間÷2=40時間まで就労できる。
産後パパ育休中の社会保険料は
月中14日以上の休業による社会保険料免除については、就労した日は休業日数に含まれませんが、場合によっては免除にならない可能性があります。就労すると、その日数や賃金は出生時育児休業給付金の調整対象となります。場合によっては不支給になることも。
産後パパ育休中の就労される場合の注意点
厚労省からの指針で、「育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業については、事業主から労働者に対して就業可能日等の申し出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされてはならないものであること。」とされており注意が必要です。
また、従業員に対して就業を申し出ない、就業の同意を撤回、会社の意に反する就業日の指定をすることによる、解雇などの不利益的取り扱いは禁止されています。