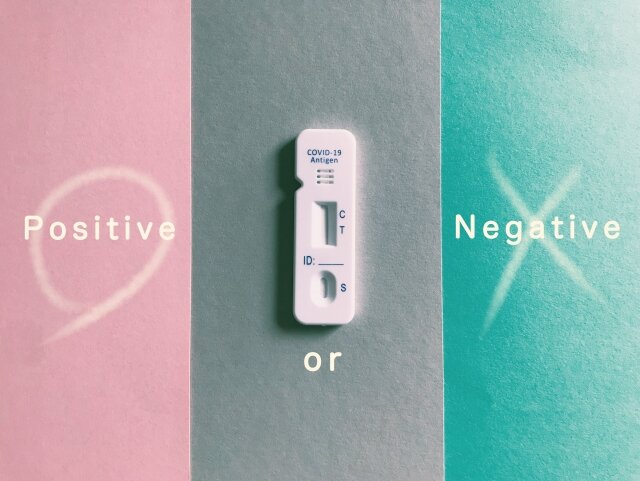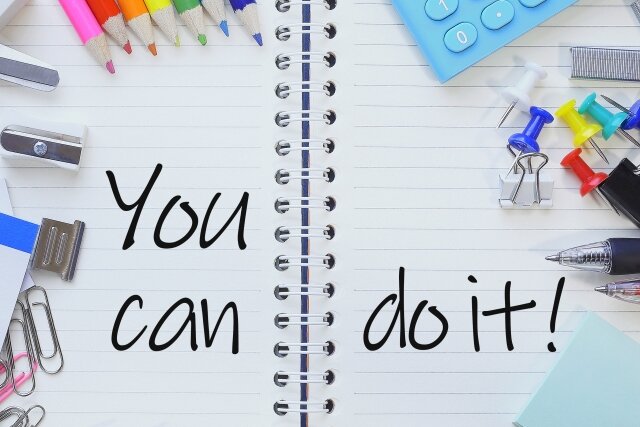産業お役立ちコラム
調味料の糖質量について

今では世界でも注目されるようになった和食ですが、料理をする上で欠かすことのできないのは「調味料」です。「料理のさしすせそ」という言葉は、砂糖、塩、酢、醤油、味噌を料理で使用する順番を指しますが、和食に限らず様々な料理で必ずと言って良いほど使用されるものばかりです。
そんな調味料ですが、使用する調味料によって料理の栄養成分も変化するのはご存知でしょうか?例えば、糖質を控えている方はごはんやパン、菓子等の糖質量には注目しがちですが、調味料にまで目を向けている方は少ないかもしれません。しかし、糖質が多い調味料を毎食摂っていると、摂取する糖質量はもちろん多くなります。そこで今回は「調味料の糖質量」をご紹介いたします。
■糖質が多い調味料と少ない調味料(100gあたりの糖質量)
多い調味料
上白糖(99.3g)、はちみつ(81.7g)、こしょう(72.0g)、みりん風調味料(55.6g)、本みりん(43.3g)
お好み焼きソース(33.5g)、米味噌・甘みそ(33.3g)、焼き肉のたれ(32.1g)、トマトケチャップ(24.0g)
少ない調味料
マーガリン(0.8g)、オリーブオイル(1.1g)、マヨネーズ(2.1g)、穀物酢(2.4g)
うすくちしょうゆ(6.1g)、バター(6.8g)、米酢(7.4g)、こいくちしょうゆ(8.6g)
■調味料を上手に使用するポイント
糖質量だけではなく、使用量も意識する
例えば、こしょうは100gあたりでは意外に糖質量が多いですが、1回使用量はわずかなので摂取量は少ないです。また、ソースなどかけて使用することが多い調味料は、「つける」を意識することで摂取量を減らすことができます。調理の際は計量スプーンを使用しましょう。
代替品を検討する
市販のドレッシングではなくて、塩、こしょうにオリーブオイルを少し加える、砂糖の代わりに糖質が約半分であるみりんを使用して調理する、糖質がカットされた市販品を使用するなどで工夫ができます。

和食はどうしても煮物や照り焼きなど、甘い味付けが多くなってしまいがちですが、煮汁を残すだけでも摂取する糖質量を少なくすることができます。調味料には糖質以外にも塩分、脂質が多いものなど様々です。これを機会に使用している調味料を見直してみるのはいかがでしょうか。